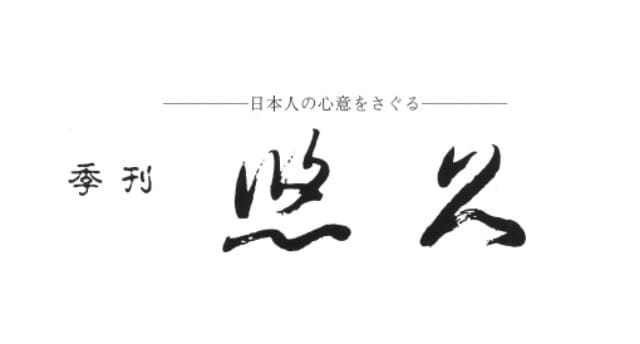観る
鎌倉巡り
鶴岡八幡宮周辺には、鎌倉の物語を今に伝えてくれる史跡が多数ございます。
当宮を起点に、物語を巡ってみてはいかがでしょうか。
鎌倉幕府の始まりと終わりを巡る
日本史上初の武家政権「鎌倉幕府」。平家追討のお告げを授けた佐助稲荷神社から、終焉の舞台である東勝寺まで、誕生と終焉の史跡を巡ります。
1.源氏山

この山の麓には、代々の源氏の邸があったため「源氏山」と呼ばれたと考えられています。また、源頼義、義家の父子が奥州征伐の時に、この山に源氏の白旗を立て、陣容を整えたという伝説も残っています。山裾には、実朝公と政子の墓と伝えられるやぐらも残っています。山頂には、鎧に身を固めた頼朝公の像が鎮座し、今も鎌倉の街を見守っています。
2. 佐助稲荷神社

流人として蛭ヶ小島に流されていた源頼朝公が病気になったとき、三晩続けて鎌倉の隠れ里の稲荷と称する白髪の翁が現れて、平家追討と天下統一を成就せよと勧めたといいます。その後幕府を開いた頼朝公はその神恩に感謝し、佐助ヶ谷にその稲荷と思われる小さな祠をみつけだし、社殿を再建したといいます。
頼朝公の源氏再興を助け、出世の後押しをしたことから「おたすけ稲荷」「出世稲荷」「勝利稲荷」とも呼ばれ、大勢の参拝者でにぎわいます。
3. 大蔵幕府跡

鎌倉入りした源頼朝公が居館を構え、初期の政権機能を置いた場所です。鶴岡八幡宮を鎌倉幕府の精神的な中核としたのに対し、ここは日常的な実務の中心となっていました。
4. 源頼朝の墓(白旗神社)

頼朝公を御祭神とする白旗神社と法華堂跡石碑を通り、石段を登っていくと、源頼朝の墓があります。質素な佇まいに思われますが、古来鎌倉は地勢を生かした“やぐら”(横穴式の墳墓)の墓所がほとんどであるのに対し、頼朝の墓は層塔の様式で祀られています。当初より有力御家人とも一線を画した特別な方として扱われていたことがわかります。
5. 仮粧坂

当時の鎌倉に入るための幹線道路であった七切り通しの1つ。鎌倉幕府終焉を招いた、新田義貞による鎌倉攻めにおいて、小袋坂・極楽寺坂と共に主戦場となりました。特に、仮粧坂は義貞自身が本体を率いて攻め込んだ場所です。その後、稲村ヶ崎に回った義貞は、鎌倉中心部まで一気に攻め入り勝利を収めました。
6. 東勝寺跡

この場所は『腹切りやぐら』としても有名です。新田義貞による鎌倉攻めによって、追い詰められた鎌倉幕府第14代執権 北条高時は諸大将と共に父祖代々の菩提寺である東勝寺へ移り、寺院に火をかけ一族283人、総勢870人余りが我先にと次々に自刃して果てました。源頼朝公が開いた鎌倉幕府はここ東勝寺にて終焉を迎えたのです。