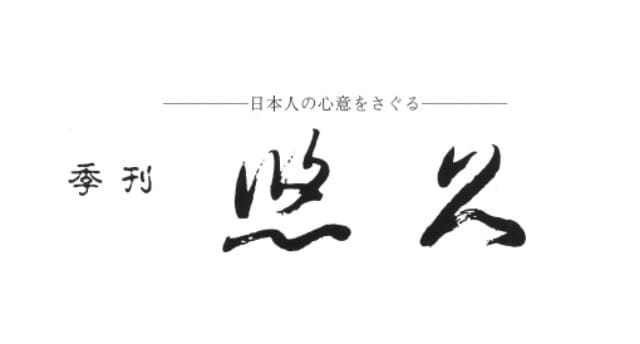ご祈祷・お守り
人生儀礼
人生の節々を祝い、神社に詣でて神様へ感謝と繁栄の祈りをささげることを人生儀礼といいます。
着帯祝
母子の健全を願う
赤ちゃんがお腹に宿った5ヶ月目の戌の日にお母さんが帯をつけるのが着帯の祝いです。安産にあやかる儀式で、結婚式の後の最初の神様への挨拶が帯祝いとなります。
命名祝
出産の無事を祝い、命名する
無事出産の暁には7日目に生れた子供の名前が決まります。これが命名祝いです。
ご両親が決める、祖父祖母に相談する等名付けの方法はさまざまですが、神様にお名前をいただくと言う意味で、神社では古来より命名式が行われています。
初宮詣
家族揃って、初めてのご挨拶
一般的に男子31日目、女子33日目にお宮参りをする風習があります。
これは母子共に神社に御挨拶できる日を取り決めた、古い習慣です。元気で健やかなお子様と御両親の神様への御挨拶、これが初宮詣の日です。
七五三祝
健やかな子供の成長を祈る
お子様の成長を祈り、3歳、5歳、7歳にそれぞれ神様にお詣りをするのが七五三祝いです。
七五三祝いは古くからある儀式に由来しています。男女共に3才の年に誕生後初めて髪を伸ばし始めることを祝う「髪置(かみおき)」。男子5才の年にはじめて袴を着けることを祝う「袴着(はかまぎ)」。女子7才の年に帯の代用をしていた付紐を取り去り、初めて帯をすることを祝う「帯解(おびとき)」。
江戸時代の徳川綱吉の子、徳松君がこの日に祝ったことから、11月15日に定着したと伝えられています。
年祝いと共に健やかな子供の成長を祈る儀式です。
| 3才 | 男女 | 髪置(かみおき) |
|---|---|---|
| 5才 | 男 | 袴着(はかまぎ) |
| 7才 | 女 | 帯解(おびとき) |
入園・入学の祝
大きな成長をご報告
成長の大きな一歩として入園・入学の式があります。入園・入学したこと報告し、これまでの成長と感謝を神様に奉告しましょう。
成人式
大人として誓いを立てる日
昔の男子の「元服」「冠礼(かんむりのれい)」「初元結(はつもとゆい)」、女子の「髪上げ」に当たる儀式で、まさに成人の式典を祝う日です。
日本人としてのけじめの日、社会人として誓いを立てる日として20歳を迎えた最初の正月に、ご神前で晴れの儀式を執行します。
当宮では、成人の日に舞殿において祭典を執行し、成人式を迎える善男善女が舞殿に昇り誓いを立てます。
結婚式
祝福につつまれ誓う、神聖な儀
めでたいご縁を頂き、新しい家庭の誕生となります。
日本人としての正装で、神前に結婚の奉告をし、新しい人生を力強く生き抜こうとする二人の姿を、両家親族を始め、多くの人々にお認め頂くことは人生最大の儀式です。
厄除
人生の転換期に無事を祈る
厄年は、それぞれ心身の転換期であり、社会的にも重要な時期といえます。特に男性の42才、女性の33才は大厄といわれ大切な時期とされています。そのような年には、厄除祈祷を受け、災厄から逃れることを祈ります。
厄除祈祷は年間を通してお受けいただけますが、特に1月下旬の土日を含む期間「鶴岡厄除大祭」が行われ、多くの方が厄除の特別なご祈祷を受けられます。
厄年表
年祝い
人生の歩みを喜び、前進する
無事に年齢を重ね喜び、力強い前進を祈るお祓いです。
(※注)還暦に該当される方につきましては厄年にも該当することから、「還暦厄除」のご祈祷をお受け頂く事が出来ます。
| 還暦 | 61歳 | 古稀 | 70歳 | 喜寿 | 77歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傘寿 | 80歳 | 米寿 | 88歳 | 卒寿 | 90歳 |
| 白寿 | 99歳 |
葬儀
神様の元へ還る
天寿を全うしてやがては一生を終えることになります。もともと人の生命は、神様から与えられたもの。しかしながら江戸時代の寺請制度以来、仏式の葬儀が定着してきました。明治以降は自由に葬儀をすることが出来るようになり、神道のやり方で先祖様をおまつりできるようになりました。
通夜祭・告別式をはじめ、帰家祭・十日祭・三十日祭・五十日祭・百日祭・年祭などの「みたままつり」、又墓苑のことなど当宮へご相談下さい。